ついに迎えてしまった検定日…いかがでしたか?翌日にはインターネットで解答も発表され…http://www.kimono-kentei.com/3級を受験した私はというと…(T_T)/~~~どぉ?なんでしょうぅ… とりあえず12月の発表まで待てみます。
さて気持を入れ替えて、最近朝晩の冷え込もきつくなって秋らしくなってきましたね。さて秋といえば衣替え、衣替えと一緒にしておきたいのが虫干し皆さんされましたか?この夏着た夏物の着物に汚れや汗シミが無いかチェックしてこれから着る袷の着物もカビやシミが無いかチェックするいいチャンスです。今日からは着物のアフターケアー(お手入れ)と保管方法を紹介します。まずは着ていた着物をかたずける編から…
・着ていた着物をかたずける編…着物を今日1日着れたことに感謝しましょう。そして後始末は誰かに頼まずに必ず自分の手で!!慣れてしまえば意外と楽しくなりますよ(^^♪
?着物を脱ぐ前に手を洗い床の上に衣装敷き(無ければたとう紙を広げた状態でも大丈夫です)を広げましょう。
?一番に足袋を脱ぎます。なぜなら意外と汚れているから。次に帯締め、帯揚げという順に着付けた順番の逆から順に解いていきます。
?脱いだら着物、帯、帯揚げ、帯締めを着物用ハンガーに掛けましょう。もし無い場合は苦肉の策普通のハンガーででも型崩れの原因にもなるので出来るだけ着物ハンガーに掛けましょう。
?風通りの良い日光の当たらない所で2?3時間干しておき、体温と湿気を取り除きます。この時忘れてならないのがシミ、汚れが無いかのチェック!もしシミや汚れがある場合は専門店に染み抜きを依頼しましょう。
? 長襦袢は半衿を取り外し着物ハンガーに掛け?と同じ方法で。
?肌襦袢と足袋は洗濯しても大丈夫ですが出来るだけ手洗いをお勧めします。
?今までの行程が済んだら当分着ないものは着付けジワや座りジワを取ってからかたずけます。アイロンをかける場合は当て布をし当て布に霧吹きをしてからアイロンがけをします絶対にスチームアイロンを使わないこと。
?あとはたたんで箪笥へしまうだけ。
さていかがですか?やっぱりいろいろと行程が有り長いですか?めんどくさいですか?でも一つ一つやりながらその日の思い出や風景を思い浮かべながらやると自然と笑顔で出来ますよ、また着物への愛着も増しますしね(^?^)ぜひご自分の手で着物をかたずけてみて下さい。
京都wabitas(ワビタス)

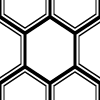
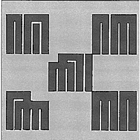
 RSS
RSS