いろいろな文様(17)
2009年1月14日 14時03分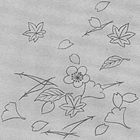
吹き寄せ文様
種々の落葉や落花が地面に集められた様子を文様にしたもので、
銀杏・紅葉・松葉・松カサ・蔦(ツタ)の葉・栗の実など、
秋風が運ぶ晩秋の風景を表わたり、
桜や菊を交えて季節にこだわらず、
自由に描かれたものもあります。風情のある文様として好まれています。
京都wabitas(ワビタス)
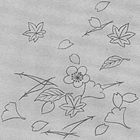
吹き寄せ文様
種々の落葉や落花が地面に集められた様子を文様にしたもので、
銀杏・紅葉・松葉・松カサ・蔦(ツタ)の葉・栗の実など、
秋風が運ぶ晩秋の風景を表わたり、
桜や菊を交えて季節にこだわらず、
自由に描かれたものもあります。風情のある文様として好まれています。
京都wabitas(ワビタス)
あらためまして、
新年明けましておめでとうございます。
昨年は、大変お世話になり、誠にありがとうございました。
今年もお客様に、喜んで頂けますよう、良品廉価を心掛け少しでもたくさんの商品をご提供できますよう頑張ってまいります。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
京都wabitas(ワビタス)
今年も残すところあと一週間となりました。
とは言っても、まだまだバタバタした日が続くとは思いますが、とにかくやり残しの無いように気をつけたいと思います。
又、あと一週間で新年がやってきます。
新たな年を明るく飾れますように!新しい商品を取りそろえるよう、そちらの準備も抜かりなく、頑張ります!!
京都wabitas(ワビタス)

仔鹿の体の模様に似ているのでこの名がつけられました。
特に鹿の子絞りで染め出した文様のことを云います。
京都wabitas(ワビタス)
せっかくお気に入りの着物を着てもなんだか着くずれしてきたり階段でつまずいたり…普段とは違う装いに戸惑いがちです。
そんなあなたに着物を美しく着るためのワンポイントアドバイス。凛とした佇まいと綺麗な立ち姿が伴って着物の美しさが発揮されるものです。一人でも多くきもの美人になっていただくべく…まずは着物を着た時の姿勢からです。
いちばん重要なのは背筋はピンと伸ばす。天井から後頭部を糸で引っ張られているイメージで背筋を伸ばします。でも肩の力は抜いてリラックス(^^♪首が長く見えて着姿が綺麗です。意外と出来る様で出来ていない背筋のピン!普段から心がけてしていると洋服姿もビシっときまります。
次に立振る舞い肩から上に手を上げない!電車に乗ったときなどつい吊革につかまってしまいますが袖口から脇が丸見えに!!注意して下さい。肘はできるだけ体から離さないようにしましょう。
着付け後のひと手間…きものを着終わった時ふと考えてみて下さい前に裾よけ、長襦袢、きものとそれぞれ2枚ずつ合計6枚もの生地が交互に重なった状態です。これはどう考えても歩きにくい!!そこで「股わり」足を肩幅より少し広めにし中腰になり、ぐっと膝を外側に、そうすると重なり合った生地に空気が入り足さばきが良くなります。無理に内股で歩くよりつま先をまっすぐに歩きやすい歩幅でゆっくりと歩いたほうが美しく見えます。
いかがですか?少しは参考になりましたでしょうか?これからは座ったとき、階段の上り下り、トイレタイムなど紹介していきます。
京都wabitas(ワビタス)
一雨ごとに寒さが増す季節となりました。
京都も、紅葉の落ち葉が目立つようになってきましたが、これが又、なかなかおつなもので…
紅葉の芝生?を踏みしめながら京都を散策!特に着物を着てとなると、ものすごく風景にマッチすると共に他から視線が集まる事も間違いなし。
今の季節は、本当に着物の似合う季節、映える季節ですよね。
明日か明後日も是非どこかに出かけてみたいです!
京都wabitas(ワビタス)
袖から見える、おしゃれを是非お楽しみ下さい。
新作、長襦袢が入荷しました!
やさしい、やわらかな配色です。ぜひご覧下さい!
http://www.wabitas.com/bizop/product_list.php?method=category&mode=normal&c=130,131&start=1
京都wabitas(ワビタス)

七宝
七宝とはもともと仏典での用語で、大変貴重だった七珍(金・銀・瑠璃・玻璃・珊瑚・めのう・しゃこ)のことです。
七宝を構成する円形は円満を示す事から吉祥文様とされます。
七宝文様は単純な紡錘円の繰り返しですが、
その文様の中に花菱を入れたりとほかの文様と組み合わせることも多く前述のように図案に空間を埋めるだけでなく、
七宝文様そのもので図案となる場合もあります。
京都wabitas(ワビタス)
皆さん衣替えはもうお済ですか?この時期にしておきたい「虫干し」について紹介します。題して「習慣にしておきたい虫干し」です
・「習慣にしておきたい虫干し」…着物をいつまでも美しく保つために
着物を湿気やカビ虫食いなどから守るためにも最低でも年に1?2回虫干しをする習慣をつけておくとお気に入りの着物をいつでも美しく着れるいい習慣です。
時期的には洋服の衣替えをする季節で湿度が低く、晴れた日のお昼前後の約3?4時間です。直射日光の当たらない場所を選び着物、帯、長襦袢を着物ハンガーに吊るします。吊るした時にシミ、変色、虫食いなどが無いかチェックしましょう。もし発見した場合は専門店やお買い上げのお店に相談される事をお勧めします。どうしても虫干しの時間が取れない時は乾燥剤を入れておくのもいいてです。着物は頻繁に着ていればあえて虫干しをする必要はありません。
頻繁に着物を着てお散歩し自然の風を通すのも着物を長持ちさせるこつです。
以上の様に虫干しを習慣づける事でお気に入りの着物を長持ちさせてあげて下さいね。ところで皆さん着物をなぜたとう紙に包むかご存じですか?和紙のたとう紙には湿気を吸う力があります。古くなったたとう紙が黄ばんでくるのは着物の代わりに湿気を吸い取っている証拠です。長くほっておくと黄変(シミ)が着物に移ってしまうのでこまめに取り換えましょう。高価なものを使うより安いたとう紙で虫干しの都度取り換えると着物も長持ちしますよ。
京都wabitas(ワビタス)
前回は「着ていた着物をかたずける編」をご紹介しますたが今回は「お気に入り着物の収納方法編」をご紹介します。
お気に入り着物の収納方法…お気に入りの着物を湿気やカビ、虫食いから守り美しく着られる様に、、、
? 着物は必ずたとう紙に包んで収納しましょう。また一枚のたとう紙に一枚の着物、帯、長襦袢です。めんどくさいからと言って一枚にまとめて入れたりしないでくださいね。あまり布や小物類は別のところに保管しましょう。そして型崩れ防止の為にはさんである紙や台紙などはすべて取り除きます。たとう紙の表に中に何が入っているか鉛筆などで書いておくのもいい手ですよ。
? たとう紙に包んだ着物はタンスか衣装箱などに入れて保管します。特に「桐」製の物は内部の湿気をほぼ一定に保ってくれるのでおすすめします。またプラスチック製のケースや紙製のケースは湿気が溜ったり虫食いの原因になります。
? 防虫剤は主に絹でできている着物には必要ありません。ただ汚れが付いたまま収納してしまうと虫が付いてしまうので収納前の汚れ、シミのチェックは必須です。もしご不安な場合はピレスロイド系の防虫剤をお勧めします。このタイプは金、銀、箔を使った物にも安心してご使用いただけます。シート状になっている物が多く、匂いが無いのが特徴です。多種類の防虫剤を併用すると科学反応が起こり溶けて衣類を汚す恐れがあるので同種類の物を使いましょう。置く位置は着物や帯、長襦袢に直接触れないように引き出しの四隅がいいですよ。
さていかがですか?たった3カ条ですがきちんと守れていますか?お気に入りの着物を長持ちさせるためにもぜひ実行してみて下さいね。次は「習慣にしておきたい虫干し編」をアップしますね。
京都wabitas(ワビタス)